為替市場入門
グラフで見る為替市場
為替市場とは
世界では、国ごとに使用する通貨が異なっている。それぞれの国の中では経済活動に使用する通貨は一つである。しかし外国と貿易をする場合は、物を購入すれば外貨を支払い、物を売れば外貨を受け取ることも発生する。このため自国通貨を外貨に、逆に外貨を自国通貨に交換する必要がある。また、外国投資をする場合も自国通貨を外貨に、投資資金を回収する場合は外貨を自国通貨に交換する。このように経済活動が国境を越えて活発になるほど、通貨と通貨の交換が行われる。一般的には、個人や企業が行う通貨の交換は、金融機関を介して行われる。顧客の注文に応じて金融機関が通貨を交換するが、その金融機関は他の金融機関とも通貨を交換する。この仲介機能を概念的に為替市場といい、交換の比率を為替レートという。
為替の動きを見る
為替は、2国間の通貨の交換比率である。日本では対円での交換比率が注目されるが、国際的には、基軸通貨である対ドルでの交換比率が代表的な指標となる。為替は、2つの通貨間の交換比率なので、ある通貨の価値を見るには、どの通貨との交換比率を見るかによって異なってくる。世界経済においては、基軸通貨であるドルとの交換比率でみるのが一般的である。日本では、円建てで外貨(円以外の通貨)の価値を見る場合が多い。通貨の交換比率である為替レートは、為替市場における2国通貨の需要と供給の変化で、常に変動している。世界経済において取引量の多い先進国通貨の過去30年の動きを見てみよう。
円建てで見る通貨
国内であれば、外貨の価値は円建てで表す場合が多い。国内の輸出企業、輸入企業とも円と外貨を取引するので、企業の業績や日本経済への影響度は、円建てでの外貨の動きに注目する。
対円で見た主要通貨30年の動き
対円で見た全般的な動きは、ドル円と、それ以外の通貨(クロス円)の2パターンに分けられる。ドル円は、過去、上昇下降を繰り返してきたが、全般的なトレンドとしてはドル安円高の方向に進んでいる。特に07年からドル安が進み、08年のリーマンショック時には、急激にドル安となった。ただし他通貨と比べれば、上下の変動は小さい。
ドル以外のクロス円では、過去、ドル以外の通貨は比較的同様な動きとなっている。これは、クロス円が、ドル以外の通貨のドル建てレートとドル円レートの積で計算されるため、ドル円レートの上昇下降の動きがクロス円レートの動きに大きく反映されるためである。上下の変動もドル円の変動より大きくなる。
 為替レートの推移(対円)
為替レートの推移(対円)ドル建てで見る通貨
ドルは世界の基軸通貨である。ドルだけが世界経済における唯一の現金とも言える。よってドル建てで表す通貨の価値は、世界での通貨価値の基準を示している。また為替取引においては、ドル以外の通貨間の直接取引はほとんどない。ドル以外の通貨間の取引では、Aという通貨をいったんドルに換え、そのドルをBという通貨に換えることで行われる。各通貨はドルと取引される。このため、国際的には対ドルでの交換レートが通貨の価値を表している。
対ドルで見た主要通貨30年の動き
30年程度の長期間の通貨の動きを見ると、円とスイスフランは長期的にはドルに対してずっと上昇している。ユーロ、ポンド、カナダドル、豪ドルは、長期的に似通った動きをしている。これらの通貨は、連動性が高いと捉えることができると同時に、むしろドルの方がこれらの通貨全般に対して上下動していると見ることができる。先進国通貨は、円・スイスフラン組と、ユーロ、ポンド等他の先進国通貨組に分けられる。
チャートの山と谷の位置など短期的な動きでみると、ユーロとスイスフランは、相関性が高い。これはスイス中央銀行がユーロとスイスフランの比を一定に保つべく為替介入していることが影響しています。ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドルは、連動した動きをします。これは、ドルが他の先進国通貨に対して上昇や下降をしていると見ることもできます。一方、先進国通貨の中で唯一円は、別の動きをする。
過去30年で円とスイスフランが上昇した。円とスイスフランの動きには連動性が見てとれる。それ以外の先進国通貨は、ボックス圏での動きとなっている。先進国通貨共通の動きとしては、1980年から1985年にかけて下落し、1985年に底を付け、1985年から1995年まで上昇し1995年から2002年まで下落し、2002年に底をつけ、その後上昇し、2008年のリーマンショックで円とスイスフラン以外は急落したが、現在は回復している。先進国通貨に共通的動きが見られることは、ドルの価値の変動であると解釈できる。つまり、ドルの価値が1985年と2002年にピークを付けたのである。ドイツの通貨が欧州通貨と連動しながらも高く推移していた。長期的には円、スイスフラン、ドイツマルクが上昇していた。通貨価値がその国の経済成長と連動していたことが推測できる。
全般的な動きは、円ドルと、それ以外の通貨(ユーロ等)ドルの2パターンに分けられる。スイスフランとユーロは一致して動く。ユーロとの連動性が高い順に、スイスフラン、ポンド、オーストラリアドル、カナダドルとなる。99年~08年7月までユーロと円は弱い正相関があったが、08年7月以降は、強い逆相関(円は急上昇、他通貨は急落)となっている。近年は、円とスイスフランに連動性が見られる。
他通貨(ユーロ等)がドルに対して同様の動きを示すことは、他通貨(ユーロ等)側の要因で為替が動くというよりは、ドル側の要因で為替が動いていることを示している。
円ドルは、他通貨に比べ上下の変動幅は小さい。全般的なトレンドでは、上下動を繰り返しながらも上昇傾向にある。一方、円以外の通貨対ドルでは、全般的な傾向としては、上下動を繰り返しながらも上昇傾向にある。
他通貨のユーロドルとの相関性では、スイスフランが相関0.9~1で、きわめて高い。相関が高い順に、スイスフラン、ポンド、オーストラリアドル、カナダドル、円となる。円はユーロドルと逆相関になることもある。
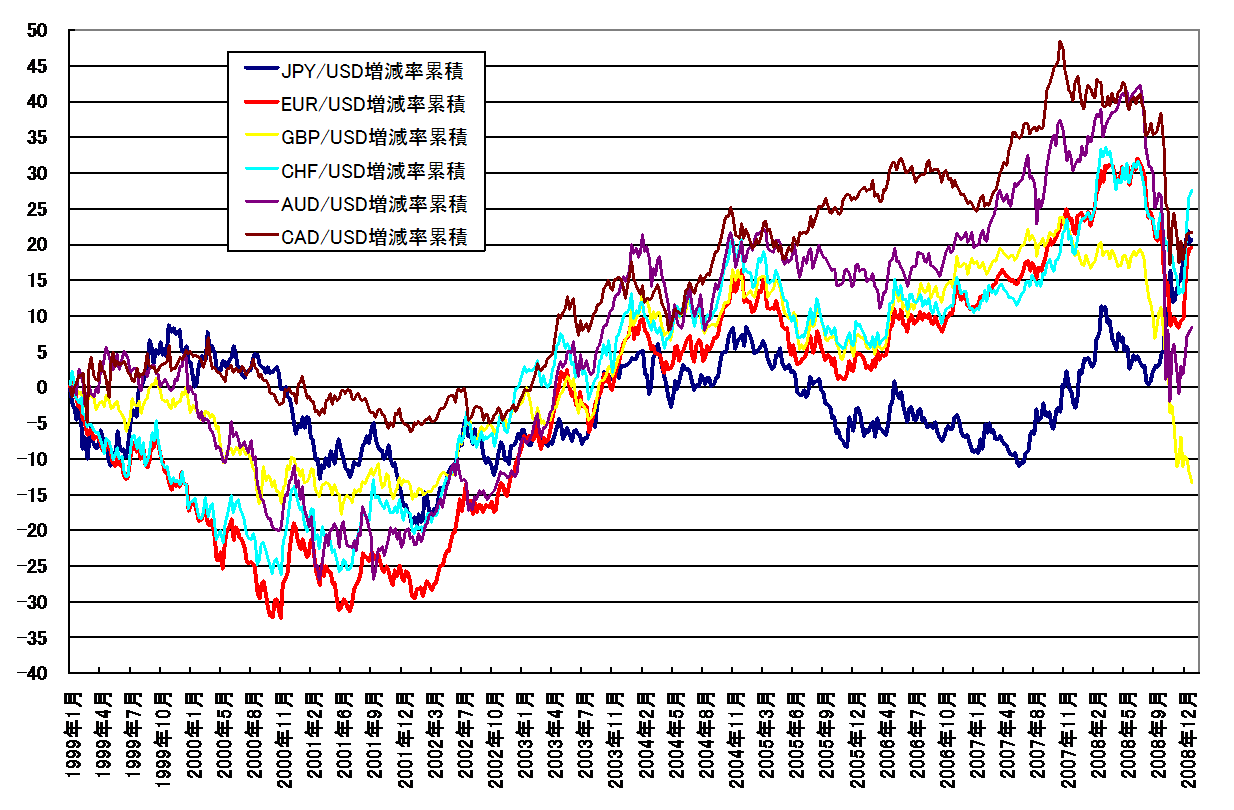 為替レートの推移(対ドル)
為替レートの推移(対ドル)為替レートのボラティティ
為替は時々刻々と変動している。変動の激しさをボラティリティという。統計学的には、為替の変動率を一定期間集め標準偏差をとったものである。為替レートの日々の変動率のばらつき具合を見るために、20日間の標準偏差を計算した。ボラティリティの大きさを見れば、為替の変動の程度が分かる。
対円で見た主要通貨のボラティリティ(変動の程度)の大きさを見ると、08年秋まではほぼ一定であるが、08年秋のリーマンショック時に急上昇した。ボラティリティの大きさを通貨間の比較で見ると、ボラティリティの高い順に、オーストラリアドル、カナダドル、ポンド、ユーロ、スイスフラン、ドルの順となる。
対ドルで見た主要通貨のボラティリティでは、08年秋までほぼ一定であったが、08年秋に急上昇(特にオーストラリアドル)している。ボラティリティはオーストラリアドルが他の通貨より高く、他の通貨はそれほど差がない。変動率は、大きい順に、オーストラリアドル、ポンド、カナダドル、ユーロ、スイスフラン、円の順である。
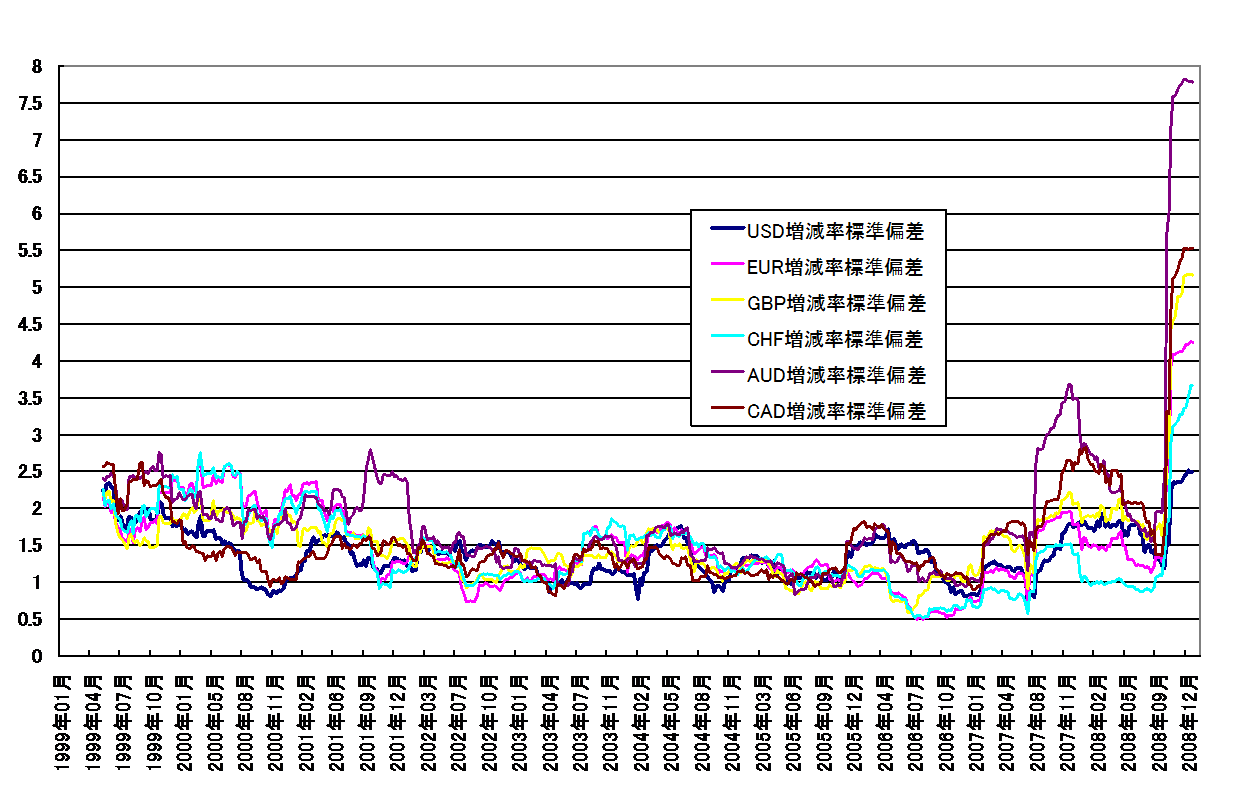 ボラティリティの推移(対円)
ボラティリティの推移(対円) ボラティリティの推移(対ドル)
ボラティリティの推移(対ドル)ドルの価値の動き
米国と外国との貿易比で加重平均した指標を使うことで、ドルの絶対的価値の変化を捉えることができる。主要通貨で加重平均した指数で見ると、1985年と2002年にピークを付けているが、40年間でドルの価値は低下してきている。1980年代前半はドル高時代、80年代後半から90年代前半までドル安時代、90年代後半から2002年までドル高、そしてその後はドル安時代というように、5~10年間隔でドル高ドル安を交互に繰り返している。経常収支とドルの価値の関係は、上下動の一致性は弱いが全般的傾向として経常収支が赤字でドルの減価が続いており整合的ではある。金利とドルを比較すると、10年債の実質金利とドルの価値は連動性が高いことがわかる。
円、ドル以外の通貨建てで見る通貨
ドル以外の通貨間の取引はほとんどないことを考えれば、ある通貨の価値を別の通貨で測るには、ある通貨のドル建て価格と、別の通貨のドル建て価格で除して計算できる。ある通貨を円建てで見るには、通貨のドル建て価格に円ドルレートを掛け合わせればよい。
合成指数
為替レートは、2つの通貨間の相対的価値を表すものである。ある通貨に注目して、その為替の動きを測るのに、別の通貨(通常はドル)との相対的関係しかわからない。例えば、円の価値の動きを測るのに、対ドル、対ユーロ、対ポンドで見て、それぞれに対して円の価値が上昇したり下降したりしている場合がある。ある通貨に注目してその価値を測るため、幾つかの為替レートを合成し、ある通貨の、それ以外の通貨全体に対する価値の変化を表したものが合成指数である。合成指数には代表的なものに以下のものがある。
実効為替レート
貿易相手国と自国の為替レートを貿易の比率で加重平均したもの。貿易相手国から見た自国の通貨の価値を表す。為替レートの変化によって、自国の貿易がどれくらい影響を受けるかが分かる。通貨の価値を表す指標の一つだが、貿易量の比で加重平均するため、それぞれの国で計算する実効為替レートは計算式自体が異なる。国際金融市場での通貨取引の量の比ではないので、注意が必要である。
円については日本銀行が、ドルについては、FRBが対主要通貨の指数を計算している。これを見ると、円とドルは対照的な動きを示している。円は多少の上下動をしながらも長期にわたって、ほぼ一貫して価値が上昇している。一方ドルは、長期的には、ほぼ一貫して価値が下落している。
実質為替レート
為替レートは、通貨間の交換比率を表すものであるが、通貨の持つ購買力という視点に立つと、物価の変化の影響も考える必要がある。ドル円を例にとる。為替レートが1ドル=100円なら、これは100円の現金で1ドルの物が買えることを意味する。米国で物価が3%上昇した場合、約103円ないと同じものが買えなくなる。一方日本では物価上昇が1%だとしたら、1.01ドルないと同じものが買えなくなる。日米間でのインフレ率の差2%を為替レートに反映させ、1ドル=102円と計算したものが実質為替レートとなる。
実質実効為替レート
実効為替レートに物価の変化を反映させたものが、実質実効為替レートである。計算は、2国間の為替レートに2国間の物価の相対的変化を加えて、2国間の実質為替レートを求める。自国と相手国の実質為替レートを貿易の比率で加重平均して自国の実質為替レートを計算する。
単純加算合成為替レート
円とドルについて、それ以外の先進国通貨(ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル)に対するレートを単純加算したものを合成指数とした指数を示す。合成指数としては、実効為替レートが代表的であるが、その国の貿易比率で重みづけされた指数であるため、それぞれの国によって、計算方法が異なるのが難点である。貿易の比率ではなく単純にレートを合成したものが、国際金融市場での通貨の価値を表すのに適していると考える。
ドル総合指数は、ドルと他通貨の為替レートの変化を単純加算したもの。これを見ると、99年~02年2月に上昇し、02年2月~04年は下落し、05年に上昇、06年~08年7月は下落し、08年7月以降は上昇している。
円総合指数は、円と他通貨の為替レートの変化を単純加算したもの。これを見ると、99年~00年は上昇、01年2月~07年7月は下落、07年7月以降は上昇、08年7月以降は急上昇している。
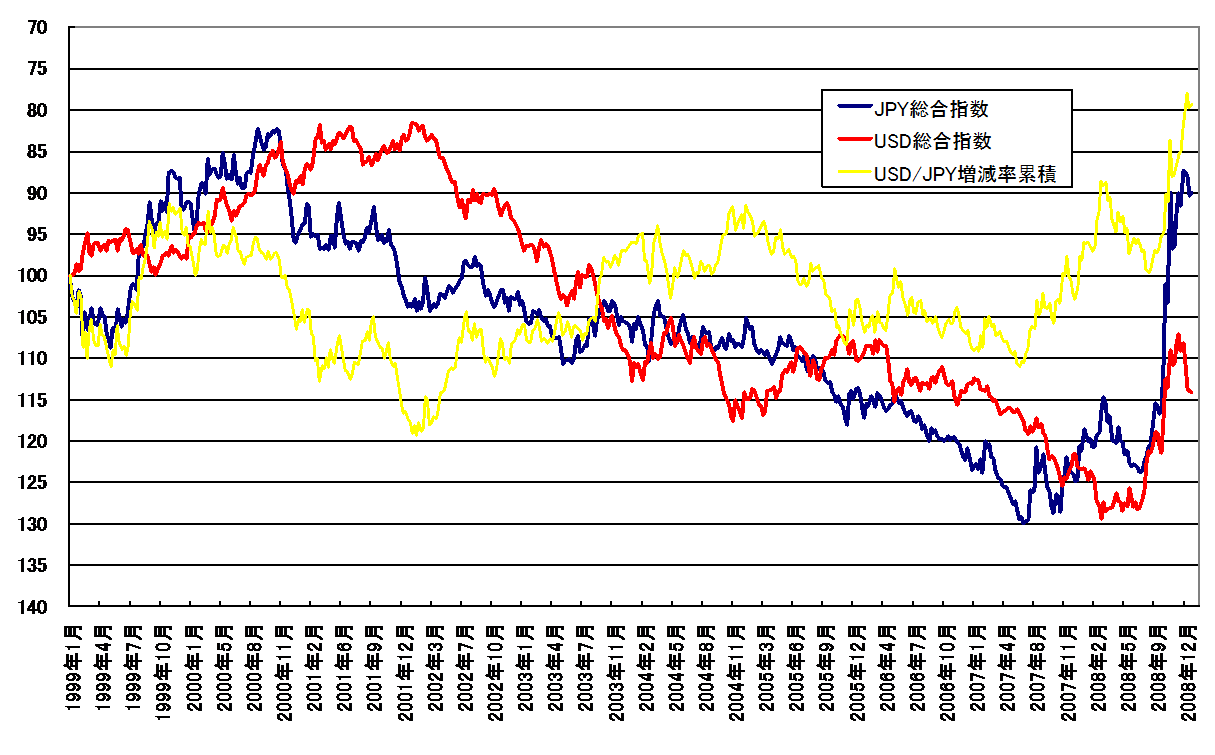 単純加算合成為替レートの推移
単純加算合成為替レートの推移通貨の価値は何で測るか
円の価値が時系列的にどう変化してきているかを考えてみる。まず最初にチェックすべきは、ドルとの交換レートである。貿易においても投資においても、円と外貨との交換で最も多いのはドルである。輸入品の7割、輸出品の6割がドル建てでの取引である。ドルとの交換レートの変化は、日本経済に与える影響の大きさから注目される。またドルは世界の基軸通貨であり、この「基準」と比較することで、通貨の価値を表すのは自然である。ドル以外の通貨との価値を比較する際にも両者をドル建てにしておけば比較しやすい。次にチェックすべきなのは、実効為替レートである。貿易比率での加重平均であるので、貿易での影響を捉えやすい。このレートで円高となれば、輸入品が安く購入でき、輸出品は受け取る円が少なくなることを意味する。実質実効為替レートでは、さらにインフレ分を調整しているので、通貨の真の価値を把握しやすくなる。ドル円レートでみた円の動きは前述したように、円高トレンドであり、近年はその傾向が強くなっている。一方、実質実効為替レートで見た場合は、円高傾向にあるにしてもそれほどの円高でもない。では、どの指標が適切かといえば、一番単純なドル円レートであると考える。合成指数は合成の仕方で値が変わること、現代においては為替取引の動機は貿易のためというよりも国際金融市場における取引の側面が強く、貿易比での合成や、物価水準の動きの考慮の必要性が小さくなってきているからである。
ドルとの比較の意味
通貨をドル建てで表すことは、ドルの価値が不変であることを前提としている。しかし実際は、ドルは米国の通貨であり、米国の経済、金融政策、国際金融のトレンドで他の通貨同様変化すると考えるのが自然である。よって、ドル円の為替レートが変化した場合、円の価値が向上したのか、ドルの価値が下落したのかは、分からない。しかし、他の通貨のドル建てでの動きを見ると、ドルの価値の変化を推測することができる。前述した主要国通貨(ドル建て)は、過去長期間同様な動きをしている。これは、個々の国の事情で為替が動いているというよりも、ドルの事情で各国通貨の為替が動いていることを示唆している。ドルの事情は、主に①米国内経済の状況、②米国の金融政策、③世界経済のリスクの3つである。
米国内経済の状況では、好景気であれば経済活動に必要なドルの貨幣需要が高まり、為替市場におけるドルの需要増でドル高外貨安となりやすい。反対に不景気であれば、ドルの貨幣需要が減少しドル安外貨高となりやすい。米国の金融政策では、金融緩和で低金利となれば、為替市場で低金利通貨のドルを売って高金利通貨を買う動きが増加し、ドル安外貨高となる。金融緩和でドルの供給が増えれば、需給の変化でドル安外貨高となる。金融引き締めの場合は逆の動きとなる。世界経済のリスクでは、政治経済上のリスクが高まると、基軸通貨であり世界経済の現金であるドルが買われやすくなり、ドル高外貨安となる。
各通貨の性質
円ドル
長期間でみれば、ほぼ一貫して上昇している。特にここ数年はその傾向が顕著である。他の先進国の通貨がユーロと似た動きをするのに対して、円の動きだけが独特である。短期的な連動性は低いが、長期的にはスイスフランと同様な動きである。円の特徴は安全通貨とみられていることだ。従来は「有事のドル」といわれ、国際経済が不透明になるとドルが買われた。これは基軸通貨であるドルが現金で、他の通貨はドルに対するリスク資産とみられ、有事の際の現金化を意味している。しかし近年、経済が不透明になる、または有事が起きると、ドルに対して円が買われ円高となる。この傾向はスイスフランにも当てはまるが、円とスイスフランとの関係では、円の方がより買われる。データの分析では、日本と米国の長期金利差の動きと為替レートの連動性が見て取れる。日本の長期金利は低く変動が小さいので、便宜上、米国の長期金利の動きだけを見ても、為替との連動性は高い。
ユーロドル
為替の取引量では、ユーロとドルが一番大きい。このため、国際金融では、ユーロドルの動きが為替市場の動きを代表したものとなる。ユーロの価値の変化だけでなく、ドルの価値の変化も表している。ユーロの動きは3段階に分けられる。ユーロ導入当初は、ドルに対して大きく下がり続けた。ユーロによって欧州の多数の通貨が統合された結果、投資機会を求めてユーロ圏外の通貨が買われたためともいわれる。その後、ITバブル崩壊後の世界経済の回復につれてユーロが上昇した。ユーロの金利は高く、高金利通貨の代表として、買われた。しかし、その後、サブプライムショックにより急落、リバウンドしたが今度はギリシャ問題で再び下落した。ユーロは中央銀行総裁の発言でも上下しやすい。物価水準に注目しており、インフレが進むと、利上げ、ユーロ高と反応しやすい。米国でもインフレに注目し金利水準を決めるが注目すべきはエネルギー価格の扱いである。エネルギーが必需品となっている米国では、エネルギー価格が上昇すると消費低迷による景気減速をにらんで利上げとはなりにくいが、ユーロ圏では、エネルギー価格上昇によるインフレを警戒し、利上げとなりやすい。
豪ドルドル
豪ドルは、ユーロとの連動性が高いが、ボラティリティは高く、先進国通貨の中では上下動が一番激しい。豪ドルは高金利通貨の代表格。基軸通貨であるドルに対するレートは、ドル円と並んで高金利通貨へのキャリートレード(低金利通貨を売り高金利通貨で運用する。)の程度を図る尺度となる。また、豪ドルは、個人投資家に人気の通貨で、国内においても海外においても、個人投資家の特にリスクの程度を図る尺度ともなる。リスク志向となると豪ドルは買われ上昇する。逆にリスク回避的になると豪ドルは売られ下落する。豪ドルはカナダドルと並んで資源国通貨でもあり、国際商品価格が上昇するとつられて高くなりやすい。
スイスフランドル
スイスフランは、円と並んで安全通貨といわれる。昔は基軸通貨のドルも安全通貨であったが、今はスイスフランと円の2つである。投資家のリスク回避的志向が強まると買われて上昇する。スイスフラン円を見ればこの2つのうちどちらがより安全通貨とみられているかが分かる。スイスフランは円と並んで低金利通貨の代表各であるが、近年は基軸通貨のドルも低金利化しており、スイスフランと円の特徴とはいえなくなった。スイスは中立国でユーロ加盟国ではないが、スイス中央銀行の為替介入により、ユーロとの比率が一定に保たれてきた。投資家もこれを知った上でスイスフランを売買するので、中央銀行の為替介入がなくても、ユーロと連動することになる。
為替を動かす要因
為替レートの過去の動きを見れば、上下動を繰り返しているのがわかる。為替を動かす要因は何か。幾つかの要因を考えてみる。
経済との関係
その国の経済が発展すれば、一般に貨幣需要の増大、国内投資の拡大、輸出が伸びれば、母国通貨への交換需要が発生し、通貨価値は高くなる。現在の経済のグローバル化を考えると、ある国だけが経済発展することは考えにくく、先進国であればどの国も経済発展するか景気後退に見舞われるとなりやすい。この場合、為替は、経済力の変化の相対的関係の影響を受けることになる。その国が、ある国より経済発展していれば、ある国の通貨に対して自国通貨が高くなりやすい。しかし、経済発展の動きは時々刻々と変化し、また予想もつかないので、現在の相場が、経済力の変化の相対的関係を常に示しているとは限らない。
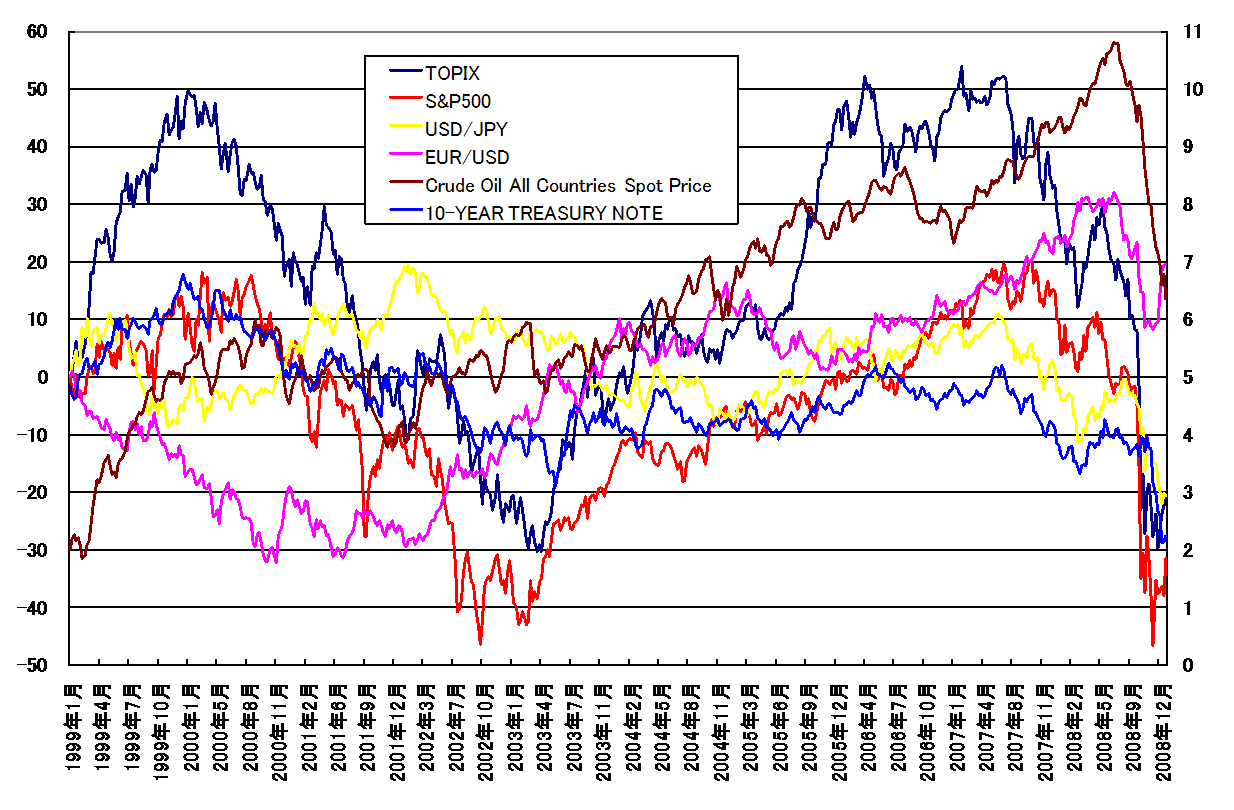 主要経済指標と為替レートの推移
主要経済指標と為替レートの推移GDPとの関係
経済の規模を表す代表的指標は国内総生産(GDP)である。GDPの絶対水準よりも、その変化(成長率)に注目した場合、経済成長が大きければ、その国の通貨の貨幣需要は増す。よって、通貨の価値は上昇すると考えられる。しかし、通貨の価値は相対てきなもので、価値を測る元となる通貨の国でも経済成長していれば、経済成長の相対的関係で見る必要がある。下図は、日本のGDPと米国のGDP、ドル円レートを示したものである。仮説は前述したとおりであるが、実際のドル円レートは、日米の経済成長の差とは連動性がないように見える。
 日米のGDPとドル円レート
日米のGDPとドル円レート国際収支との関係
通貨を交換し外貨を得るのは、外国と取引を行うときである。外国との取引は国際収支統計で記録される。注目ポイントは、貿易収支と所得収支である。貿易収支や所得収支が黒字の場合は、企業が製品を輸出して外貨を稼いでいる、ないしは外国投資から利子・配当等の外貨を得ていることを表し、いづれは自国通貨に交換することが予想される。このため、貿易収支や所得収支が黒字の場合は、その国の通貨は買われやすく上昇しやすいと言える。
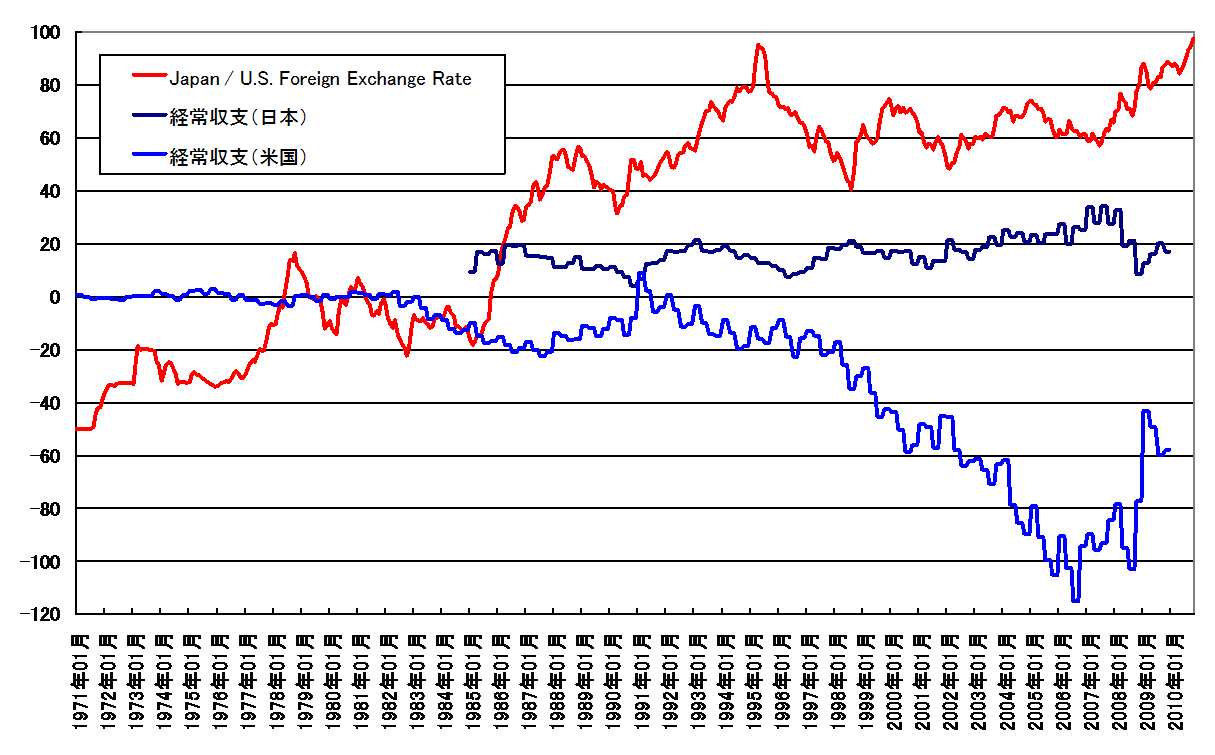 国際収支とドル円レート
国際収支とドル円レート金利との関係
A国の金利がB国の金利より高い場合、A国の通貨を調達しA国で運用した方がB国で運用するより得になる。よって、B国の通貨は売られA国の通貨が買われることになる。金利が高い国の通貨は金利が低い国の通貨に対して価値が高くなる。では、どこまで高くなるのか。2つの考え方がある。
一つは裁定価格である。A国がB国より金利が高いと、1年後A国の通貨で運用した方がB国の通貨で運用するより利益がでる。それなら、皆A国の通貨で運用しようとするので、A通貨が値上がりするが、どこまで値上がりするか。A通貨を手に入れれば得られるB通貨に対する超過金利分がA通貨のB通貨に対する期待リターンと相殺するところまでである。A通貨から得られるリターンとB通貨から得られるリターンが等しくなるまでA通貨は値上がりする。
もう一つは、金利差の変化である。現時点での金利差は、すでに市場関係者には知られている。市場で形成されている価格は、すでに各国の金利差を織り込んでいると言える。とすると金利差がそのままであれば、為替は変化しない。実際、各国中央銀行が決める政策金利は変化しなくても、政策金利以外の金利(例えば長期金利)は市場で時々刻々と価格が形成されるため、金利差は動くことになる。それにつれて為替も動く。
政策金利とドル円レート
経済学では、上記の理論はアセットアプローチと呼ばれ、為替レートの主要な決定要因と見られている。ドル円レートと日本及び米国の金利の関係を実際のデータで見てみる。日本の政策金利は、ほぼゼロ近辺で張り付いているので、米国の政策金利(FF金利)だけを取り上げる。これをまた日米金利差の代理変数とみても差しつかえない。30年の長期間で見てみて、FF金利は、80年近辺に大きピークを付け、その後上下動しながらも、低下傾向を示している。30年間の前半では、金利とドル円で相関は見られないが、後半では、何らかの連動性が見てとれる。特に近年10年間は、時間差はあるにしても、FF金利の上昇下降と為替レートの変化に対応関係がある。
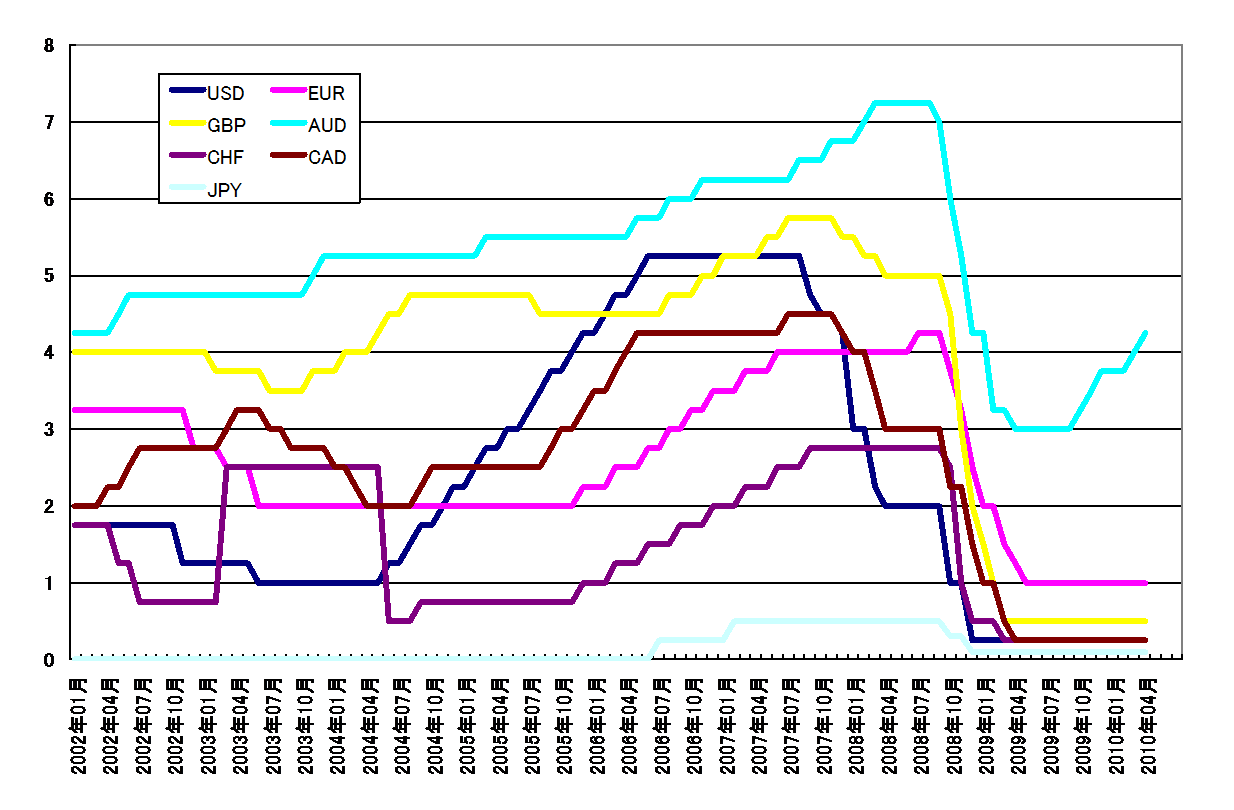 各国政策金利の推移
各国政策金利の推移 米国政策金利とドル円レート
米国政策金利とドル円レート米国長期金利とドル円レート
金利には政策金利のような短期金利から国際10年物のような長期のものまである。下図は、米国の長期金利の代表的指標である米国債10年物とドル円レートを表したものである。01年以前は相関性は見てとれないが、01年以降、連動性が観測される。特に07年以降はほぼ同じ動きをしており、連動性が顕著である。米国債5年物とドル円レートとの連動性はより高くなる。一般的に、ドル円レートとの連動性が注目されるのは、米国債2年物金利である。
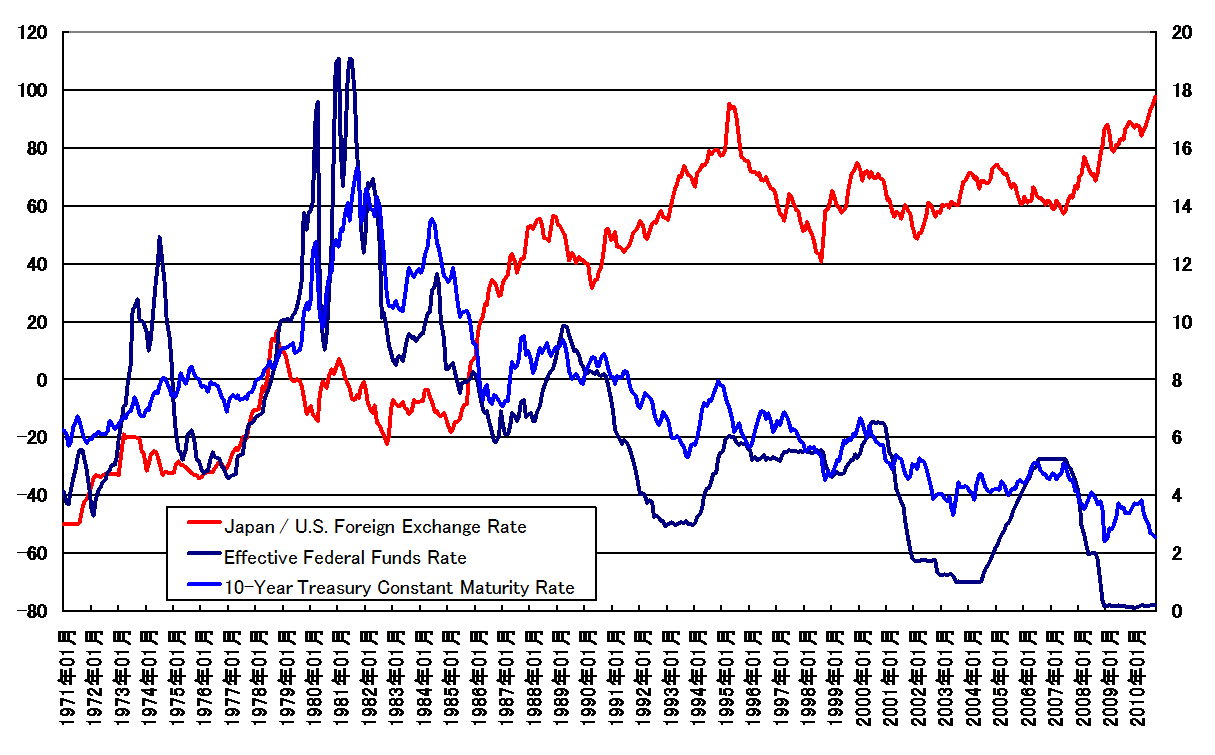 米国債10年物名目金利とドル円レート
米国債10年物名目金利とドル円レート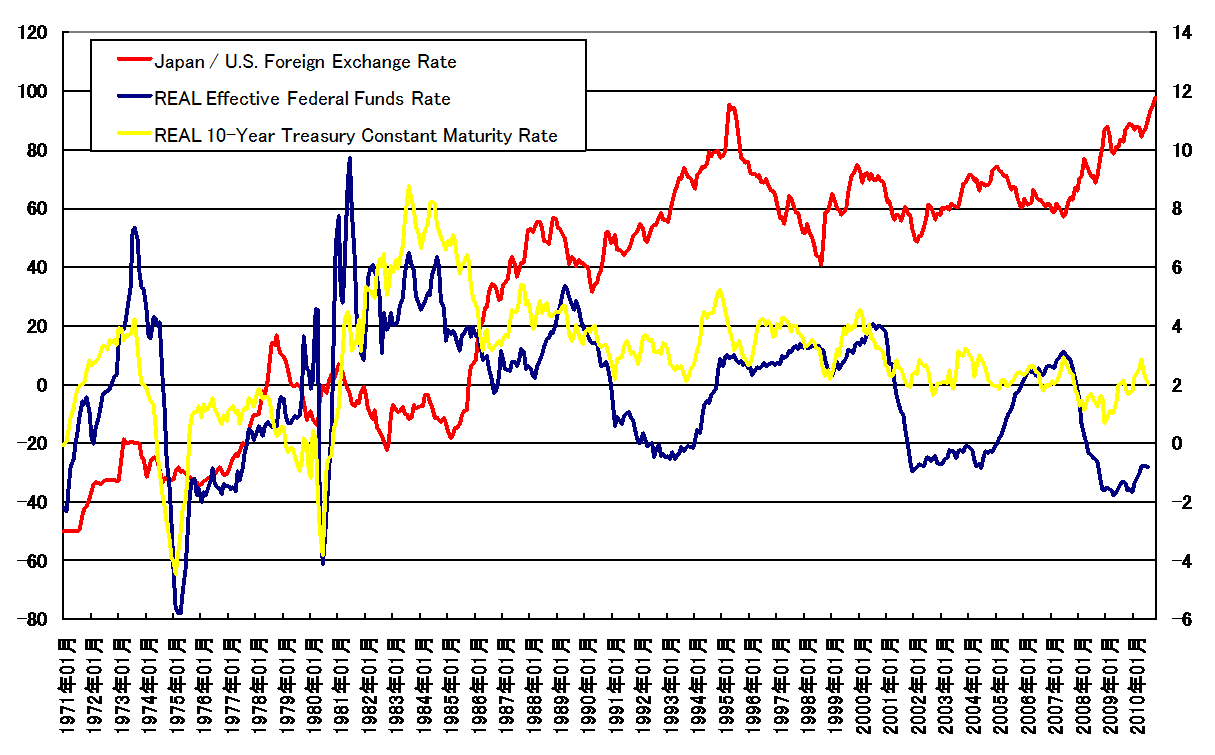 米国債10年物実質金利とドル円レート
米国債10年物実質金利とドル円レート物価との関係
為替の絶対水準はなんで決まるかについて、一般的な考え方があります。購買力平価仮説です。これは仮説の一つであって、実際にこのとおりに為替の水準が決まっているわけではありません。
購買力平価仮説は、一物一価の考え方です。物の価値は世界どこへいっても同じと考えます。あるものが日本で100円、それと全く同じものが米国で1ドルなら、100円=1ドルとなります。この比率は財ごとに異なりますし、また日本と米国でまったく同じものを見つけるのもたいへんです。そこで便宜的に、物価の水準の相対的動きに注目します。例えば日本の物価水準が昨年より1%上昇し、米国の物価水準が3%上昇したなら、1年間で2%分の価格差がつきます。日本と米国で同じものが売られているとするならば、この2%分は、ドル円の為替レートが2%円高になることで達成されます。
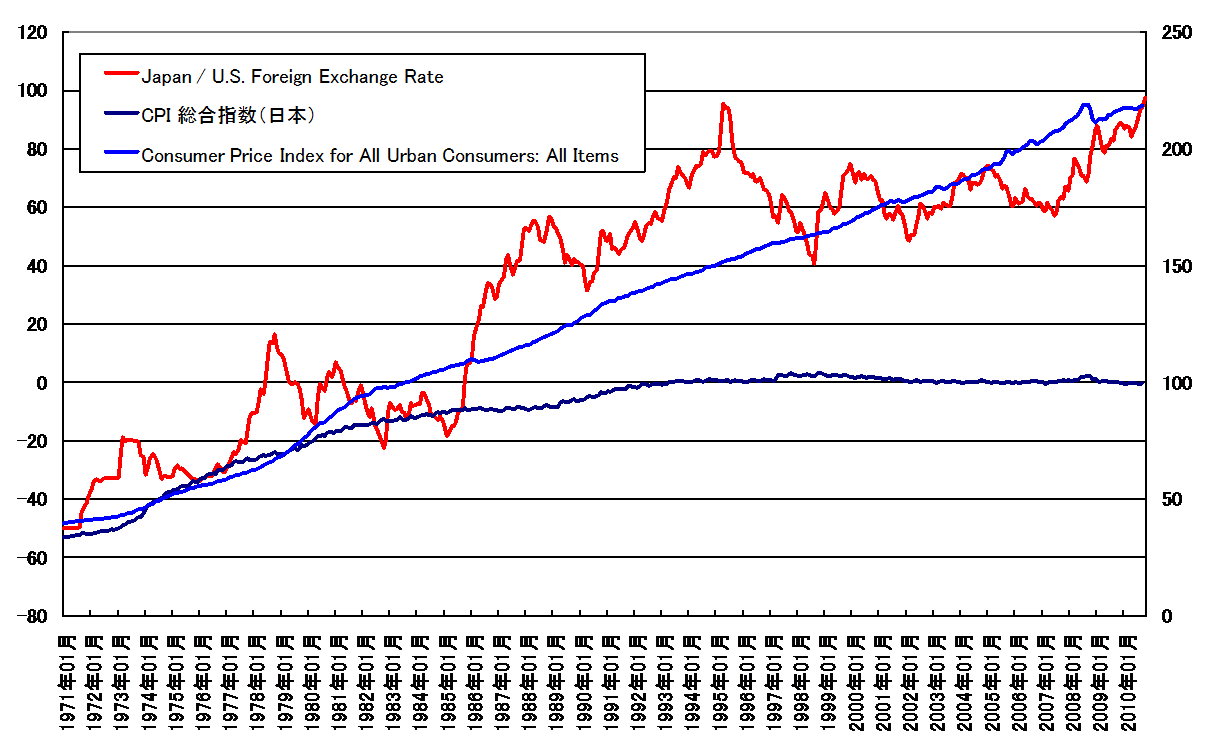 物価とドル円レート
物価とドル円レートこの仮説は、ドル円の長期的なチャートを分析すると、有る程度の整合性があると言われています。20~30年の長期のスパンで見て、仮説が成り立つように見えても、それより短い期間でも為替は大きく変動しています。その変動への説明力はありません。また、ドル円以外の通貨の組み合わせでは、長期においても必ずしも整合的というわけではなく、為替変動の考え方の一つと考えておけばよいでしょう。
株価との関係
株価は経済が発展すれば値上がりします。通常は経済発展が続くので、株価は上昇している期間が長くなりますが、為替は国同士の相対的関係で決まるので、株価のように長期間上昇することはありません。また株価の場合は、連動性があり、どこの国の株価も上昇するといったことはありますが、為替は相対的関係できまるので、どこの国の通貨も上昇するといったことはなく、株価との連動性はありません。
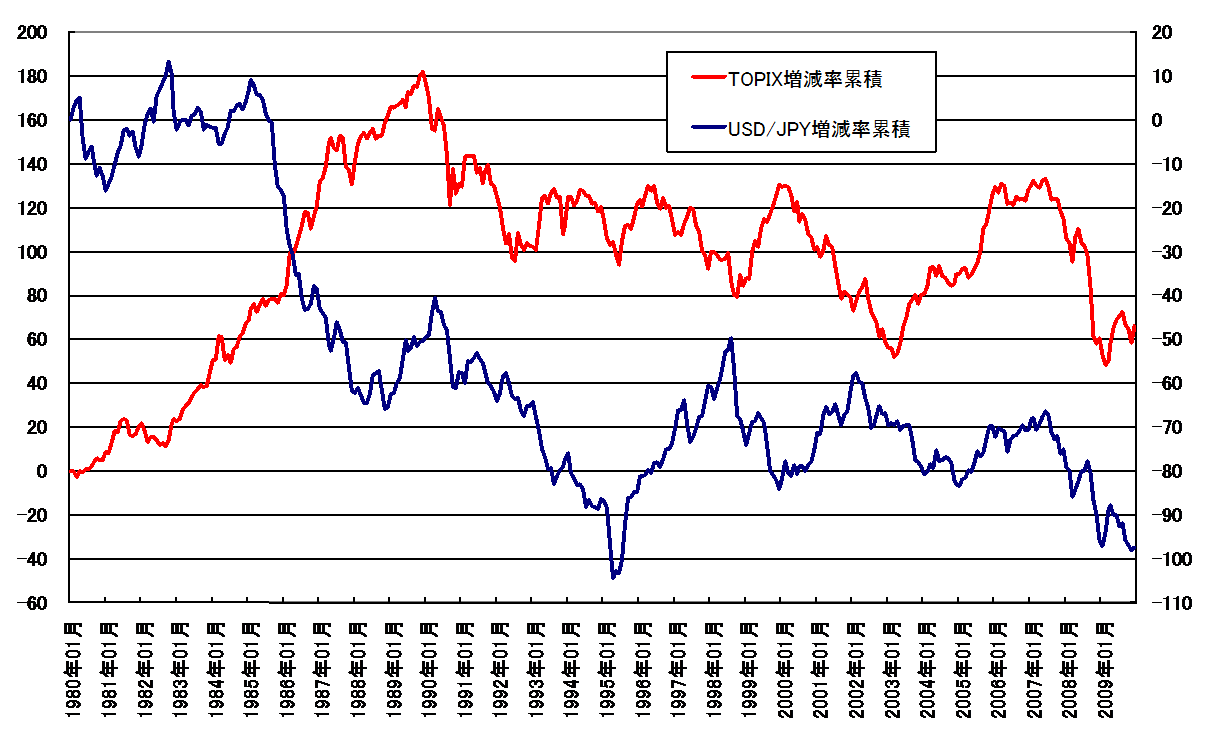 日本株価とドル円レート
日本株価とドル円レート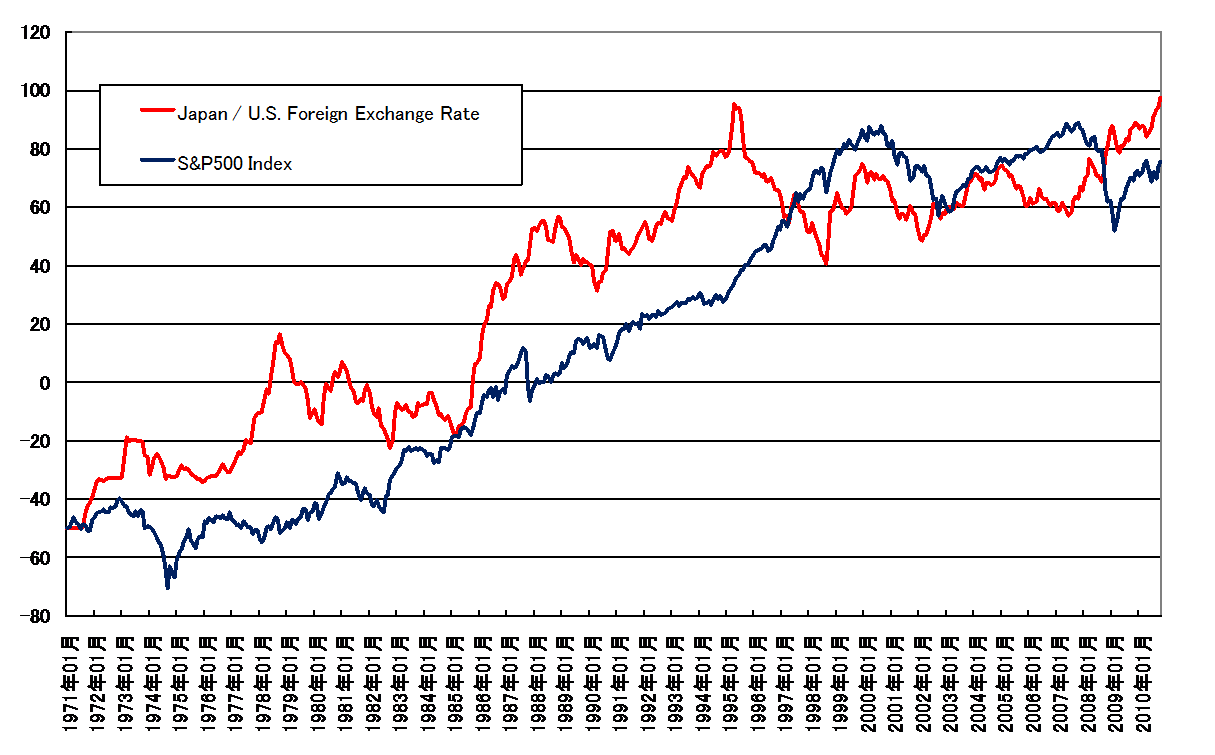 米国株価とドル円レート
米国株価とドル円レート中央銀行の行動との関係
為替介入
中央銀行は為替相場の調整のために、為替介入を行います。介入が自国通貨売り、外国通貨買いの場合は、外貨準備が積み上がります。この外貨を現金のまま長期に保有することは少なく、外国債券を購入し運用する場合が多いです。このとき、持っている外貨を別の国の債権を購入しようとする場合に外貨の売買が発生します。中央銀行は、取り扱う量が大きいので、その行動が為替の変動につながります。
金利政策
金融政策では、中央銀行が銀行間取引市場の売買に介入し短期金利を目標金利に誘導します。誘導された短期金利によって長期金利が間接的に誘導されます。目標金利の上げ下げによって短期長期の金利が上げ下げされ、外国との相対的な金利差が拡大したり縮小したりします。金利差の変化は為替の変化をもたらします。
量的緩和政策
短期金利の制御だけでなく、中央銀行が供給する貨幣の量を制御することで、金利制御と同様な効果をもたらします。中央銀行が様々な債権や金融商品を購入し貨幣を供給することで、対象国の金利の低下をもたらし、通貨間金利差の縮小(又は拡大)を通じて、為替相場に影響を与えます。債券購入による金利低下の直接的効果だけでなく、貨幣の流通量拡大による貨幣そのものの価値の低下(物価の上昇)と外国通貨に対する相対的な価値の低下は自国通貨の下落をもたらします。二国間の貨幣供給量の相対的変化が為替レートの変化を生じさせる原因となります。
企業行動との関係
輸出入を行う企業は、一般に輸入時に外貨で支払い、輸出時に外貨を受け取る。近年、経済のグローバル化が進み、自国だけでなく外国で利益を上げる企業が多くなっている。外貨で得た利益は、国内せいさんでのコストの支払いや国内投資、内部留保等の目的で、自国通貨に変換されることが多い。海外収益の拡大は、自国通貨高の要因となる。産業政策で税制が変更されると、国内還流が影響を受け、為替相場を変化させる可能性がある。
為替変動の季節性
企業や金融機関は、業務上、1年間の決まった時期に為替取引を行うと言われている。企業活動は、年単位、年度単位、4半期単位で区切りを設けるので、為替決済をそのタイミングで行いやすい。具体的には、日本企業では、年度末の3月、半期末の9月、4半期末の6月、12月である。欧米企業は、年末の12月、半期末の6月、4半期末の3月、9月である。このタイミングで海外で挙げた利益を自国通貨に交換する。よって、ドル円でいえば、3月に円高となり、6月に円安、9月に円高、12月に円安となる。4半期末の影響はどちらともいえない。しかし、実際の過去のデータで検証してみると、必ずしもあてはまらない。
企業は業務上一定周期で外貨の交換を行う傾向がある。例えば会計年度が近付くと外貨を自国通貨に交換するなどである。通貨の需要にも1年を通じた季節性がある。一般に、年末が近づくとクリスマス商戦などでドルの需要が増す。このため、ドルが高くなる。また、日本では、年度末が近づくと決済手段として通貨の需要が高まるため、円が高くなるといわれている。
実際の為替データで検証してみると、上記のことは当てはまらない場合も多い。ドル円についての1年間の季節性は、高パフォーマンス:6月、2月、4月であり、低パフォーマンス:10月、9月、5月、11月である。
 ドル円レートの月別騰落率
ドル円レートの月別騰落率短期的な要因
為替市場は日々刻々と動く。毎日の変動要因は何であろうか。為替市場は他のリスク資産とは異なり、通貨間の相対的関係によって価格付けられる。ドル建てでみれば他のリスク資産と同列に見ることもできるが、対象通貨とドルとの相対的関係を表しているにすぎない。
経済情報への反応
日々発せられる経済情報に対して、為替市場は瞬時に反応する。一般に、情報がポジティブサプライズであれば、その国の通貨は買われ上昇する。逆に、情報がネガティブサプライズであれば、その国の通貨は売られ下落する。しかし、近年のキャリー取引(低金利通貨を売って高金利通貨を買い、金利差分の利益を獲得しようとする投資手法)の浸透により、リスク選好度が高まると、キャリー取引の増加により高金利通貨が買われ、リスク選好度が弱まる(リスク回避的になる)と、キャリー取引の減少や反対売買の増加により高金利通貨が売られる傾向にある。経済情報により投資家のリスクに対する姿勢が変化し、それによって為替の変動が起こる。投資家がリスク選好的になると、ユーロや豪ドルが買われ上昇し、リスク回避的になると、円やスイスフランが買われ上昇する。
長期金利の変化
金利差の縮小/拡大で、高金利通貨が上昇/下降となる。
政策金利の変化
政策金利が上がれば、それにつれた長期金利の上昇が予想され、通貨が上昇する。また現在政策金利が上がらなくても、近い将来、上昇が見込めるのであれば、現在において先回り買いで上昇する。
要人の発言
政府の財務責任者や中央銀行の幹部が政策金利に関する発言を行うと、それに応じて為替が動く。市場で価格が形成される長期金利と異なり、政策金利は中央銀行が裁量で決められるので、政策金利の予想にあたって、中央銀行が何を考えているかを把握することが重要となる。要人の発言はその手掛かりを与える。また、要人側も発言することで、為替市場に今後の政策金利の変更を織り込ませようとする意図もある。
為替変動のモデル化
為替は他の金融商品と同様なモデル化ができます。一定期間の変動率を確率分布正規分布で表します。これは変動率の分布が正規分布になっているというより、分布の取り扱いの容易さで、近似的に正規分布を当てはめていると言えましょう。確率分布で表すことは、毎日の変動は独立的にランダムに起きると仮定していますが、実際はどうでしょうか。毎日の変動が独立事象ならば、N日の変動率の標準偏差は1日の変動率の標準偏差に対してルートN倍になっているはずです。実際のデータでは、Nが大きい値では、ルートN倍よりも大きくなっています。つまり独立事象とは言えず、相場が一方の方向に偏る傾向があります。
世界経済と為替
世界経済が動けば為替も動く
世界の経済が、経済成長、好不況、インフレで動けば、経済に必要な通貨の需給関係が変わり、為替は変動する。各国の金融政策、為替政策の変化は金利差の拡大縮小、為替介入を通じて為替を動かす。世界の投資家のリスクへの姿勢が変化、例えばリスクが高まれば、リスク回避で買われる通貨が買われ、リスク選好で買われる通貨が売られる。
為替が動けば世界経済も動く
例えばドル円で円高となれば、輸入品が安くなり輸入が増える一方、輸出が抑制され輸出型製造業の生産が抑えられます。輸入品の価格下落はインフレ抑制効果となります。輸出の減少は景気を抑え、経済の減速と低インフレが起きます。これは金融緩和を促します。輸入の増大と価格低下は、国内における国内企業の競争力を低下させ、また、海外市場においても、円高で日本の輸出品の価格競争力が落ち、当事国においても第三国においても外国企業との競争で不利になります。自国通貨の上昇は通貨の価値の上昇を意味するのですが、輸出立国である日本にとっては、製造業の業績低下、日本経済全体の低下につながります。
金融市場と為替
2つの金融商品に相関関係があるとき、両者は対等というより因果関係があると考えることができる場合がある。一つは、売買金額に大きく差がある場合、売買の大きい市場の動きが売買の少ない市場に影響を与えると考えるのは自然である。もう一つは、時間的に先行するものが原因で、その後に続くものが影響を受けると考えることである。為替市場は売買代金が極めて多く、為替の動きで他の市場が動くことが多い。
商品と為替
ドル安となれば商品は高くなる。国際商品市場では、商品はドル建てが多い。ドルの価値が下がっても商品自体の価値が変わらなければ、ドル建ての商品価格は上昇する。ドルの指標としては、ユーロドルが代表的である。過去データを見ても、対ユーロでのドル安が原油高、金価格上昇に繋がっている。
債券と為替
債券と為替の関係は、前述したとおり、債券価格の変動で金利が動くと、2国間金利差の変化で、為替が動く。債券の売買代金は大きく、債券の動きが為替に影響するが、為替の動きによって、例えばドル高になると米国債を自国通貨に換金することが増え、米国債の価格が下がる(金利は上昇する)ことも有りうる。
株式と為替
株式と為替の関係には相関関係がある。ただし、どちらかがどちらかの原因となるようなはっきりした因果関係は明確にできない。日本では、一般に株安と円高、株高と円安の組合せとなることが多い。この解釈は、円安になれば輸出企業の業績が上がり日本経済全体を持ち上げるから株高となる。円高の場合はその逆である。これは為替が原因で株価が結果という関係になる。また、円高になると外国人投資家が利益確定のため日本株を売り株安を招くという解釈もできる。リスクという視点では、円がリスク回避で買われる場合、世界経済のリスクが高まると円高と株安となる。この場合、両者が因果関係というよりは、リスクとの因果関係から両者に相関関係が生じているのである。
為替市場のしくみ
市場の構造
為替は世界一つのマーケットで日夜動いています。たくさんの通貨が取引されますが、通貨の交換は組合せの数だけ場合が考えられます。10カ国の通貨の交換でも10×9÷2=45通りあります。組合せの数が多いとそれだけ、交換相手を見つけるのにたいへんです。そこで実際の取引は「共通通貨」をきめて、それぞれの国の通貨は、その共通通貨との交換だけを考えればよいことになります。A国とB国の通貨を交換する場合は、A国と共通通貨との交換、共通通貨とB国通貨との交換の2段階で行えます。現在実質的に共通通貨となっているのは、ドルです。よって通貨の価値(価格)を評価するには、ドル建て価格でみるのが標準的です。市場での取引規模では、ドルが全体の半分以上を占めています。その次がユーロです。ユーロ登場以来、ユーロの比率は高まってきました。その次には、円、ポンドと続きます。
為替市場の参加者は、金融機関がメインですが、最近は個人投資家(FX取引)が増えてきており、個人投資家の影響度は増してきている。金融機関は、基本的に顧客への通貨の提供がメインで、カバー取引という形で、金融機関自らは、ポジションを取らないことが多い。このため、売買代金が多くても売りと買いが均衡し、相場の上げ下げには影響しない場合も多い。
投機筋の動きについては、CMEの建て玉情報が参考になる。CMEの建て玉で非商業部門を見るとポジションの傾向を見てとれる。ただし、これは過去の結果を示すもので、今後の予測はできない。
為替取引の量
為替取引の量は、他のどの市場、世界の株式市場、債券市場、商品市場よりも大きく、毎日膨大な取引が行われています。取引において流動性は、重要な要素の一つですが、為替市場はこれを満たしている市場です。ただし、取引が多いのは先進国の通貨で、途上国の通貨は取引量が限られます。通貨は2つの通貨の交換ですが、大部分の取引はドルとのものです。先進国通貨とドル、途上国とドルの取引が一般的です。国際決済銀行が通貨間の取引量を公表しています。それによると、ドルとユーロの取引が最も多く、次いで、ドルと円、ドルとポンドと続きます。世界各国の通貨は多数あり、組合せの数は膨大なものになりますが、取引量で見ると特定の通貨取引で全体の大部分を占めています。
為替市場の1日
為替の3大市場は、ロンドン市場、ニューヨーク市場、東京市場である。通貨取引量は、概ね4:2:1の割合であり、ロンドン市場が一番大きい。よって、為替の変動は、ロンドン市場での動きが大きくなる。ロンドン市場、ニューヨーク市場でも、始まりの時間帯に動くことが多い。また、日本の早朝の時間帯で開くオーストラリア市場は、売買が薄く為替の変動が大きくなりやすい。
- 7時~8時: オーストラリア市場で取引される。値動きが大きくなりやすい。
- 8時~16時: 東京市場で取引される。10時には中値決済といい、金融機関窓口の当日のレートが決まるため、この時刻のレートは注目されやすい。
- 16時~21時: ロンドン市場で取引される。
- 21時~6時: ニューヨーク市場で取引される。
為替取引は世界中で行われるため、24時間である。しかし、1日24時間一定の取引が続くわけではなく、市場規模の大きい先進国市場の午前午後の時間帯に主に取引される。それはニューヨーク市場、ロンドン市場、東京市場である。特にニューヨーク市場とロンドン市場が重なる時間帯は相場が動きやすい。また、取引量が極端に少なくなる時間帯も大きく動く。具体的には、日本時間の早朝、ニューヨーク市場が閉まり、東京市場が開く前の豪州市場の時間帯、午前6時~8時の時間帯である。特に月曜日の早朝は大きく変動しやすい。
為替市場の参加者
投機筋と実需筋
実需筋と投機筋に分けられる。実需筋としては、輸出入業者、金融機関など、投機筋は、機関投資家、ヘッジファンド、個人投資家などである。輸出入業者の売買動向は、輸出業者であれば、売上等で得た外貨を自国通貨に、輸入業者であれば自国通貨を外貨に換え輸入品の支払いに充てることが多い。輸出では、5割程度がドル建て、輸入では7割程度となっている。輸出入による貨幣の需要は、輸出と輸入の金額割合で、需給が決まる。よって、経常黒字であれば、外貨を円に換える需要が大きく、経常赤字であれば、円を外貨に換える需要が大きくなる。
投機筋は、実需筋の需給動向とは、別の考えで動く。値上がりしそうであれば買い、値下がりしそうであれば売る。そこで実需筋の動きに注目する。実需筋は相場の将来予想と関係なく、必要性により為替売買することが多く、経済状況や季節性から動向を予想しやすい。よって、その方向に乗っかる動きをしやすい。投機筋の売買動向を見る指標の一つにシカゴマーカンタイル市場が発表する非商業部門の建て玉がある。
銀行
為替取引では、銀行が中心的役割を担います。為替市場といっても、どこかに取引所があるわけではなく、銀行間取引システムでの取引、いわば電子的取引で行われます。個人の取引は、取引業者が銀行が取引を行っています。最近は取引所取引もあります。法人は、銀行と取引します。銀行は自らが投機的取引(自己売買)を行う場合を除いて、委託売買では、顧客の注文に従って売買します。このとき、銀行が為替変動リスクを負わないように、カバー取引を行います。カバ-取引は、対顧客取引によて、買いポジション、売りポジションが形成されたら、すぐに反対売買を他の銀行と行い、ポジションをゼロにするというものです。ポジションをゼロにすれば、為替リスクはありません。銀行は顧客との取引において、売値と買値に差をつけることで利益を得ます。相場よりも安く顧客から買い、高く売るのです。こうして為替業務を顧客の要求に応じて行ってもリスクを抱えることなく、一定の利益を得られるのです。カバー取引によって、売りと買いの同量の取引が銀行間で何度も行われるため、取引量が膨らみます。よって、為替市場は非常に売買の大きい市場ですが、その大部分は、売り買い同量の取引で、相場の価格形成に影響を与えるような投機的な売買は少数といえます。
個人
従来より為替売買では銀行の取引が多いのですが、最近注目を集めているのは、個人の取引です。個人の特徴として、株式売買同様、逆張り取引があります。相場は一定の値幅を上下するとの仮説を下に、ある程度下落すると買いを入れ、逆にある程度上昇すると売りを入れるというものです。個人の売買が大きくなれば、相場変動の抑止効果となります。個人の取引は、全体の為替取引の2割程度といわれ、相場の変動を有る程度抑えている可能性があります。為替のチャートを見ても、近年は依然ほどの為替変動を起こしていません。変動は年々小さくなっているようです。個人で人気があるのは、ドル円、豪ドル円、ポンド円です。個人の為替取引が増大するにつれ、為替形成への影響力も増しています。個人はスワップポイントに注目します。スワップポイントは、2国間の金利差分を受け取る又は支払うものです。低金利通貨(代表的なものは円)を売って高金利通貨(代表的なものは豪ドル、ユーロ)を買えば、低金利通貨の金利を払い、高金利通貨の金利を受け取ります。この場合、差し引きで受け取りとなります。このスワップポイント獲得を狙って、金利差があるときは、円が売られます。つまり、個人の取引が増えるほど、円安となります。実際、2000年代に、個人の取引が大きく上昇しましたが、大きく円安となりました。
企業
日本は、原油などのエネルギー、穀物などの食品、工業原料を輸入している。輸入業者である石油業者、穀物業者、製造業などでは、為替市場で外貨を調達し輸入の決済代金支払いに充てている。輸入品は7割程度がドル建てといわれている。よって、輸入業者は為替市場で円をドルに換えている。輸入業者にとって円高となるほど安く調達できるが、逆に円安となったときは負担増となる。このため、将来の円安の事態に備えるために、為替の先物市場で予め決めたレートで円と外貨を交換する取引(先物取引)が多い。先物市場で輸入額分の円を売っておけば、将来もこの固定レートで取引できる。このように為替市場、特に先物市場を利用して為替変動に備えることを為替予約という。一方、日本は、工業製品を輸出している。輸出業者には製造業が多い。輸出品は5割程度がドル建てといわれている。輸出業者の場合は、円高となると外貨を円に交換した場合の受け取り金額が下がるので、円高リスクに備える必要がある。輸出業者は、先物市場でドル売り円買いの為替予約を行い、為替レートを固定化する。
金融政策と為替
金融政策によって、政策金利が定まるだけでなく、インフレ予想やマクロ経済に与える影響も変化する。金利、インフレ、マクロ経済動向は、為替レートに大きく影響を与える。
為替政策の歴史
戦後、しばらくは為替取引は固定相場制であった。たとえば1ドル=360円の固定レートで取引された。世界の経済が発展し通貨の交換取引が増大するにつれ、それぞれの国の貿易量や経済規模、発展の程度の違いから通貨取引で固定した相場を続けることは困難になった。この情勢変化を受け、市場の需給で通貨の交換比率を決めるという変動相場制に移行した。ドル円では、1ドル=360円だったレートが急激に円高となり、1ドル70円台にまでなった。その後80~120円ぐらいの範囲を動いていたが現在は最高値圏にある。先進国では固定相場から変動相場へ移行したが、途上国では現在もドルとの交換レートを固定(ドルペック制)している国は多い。固定でなくても、ドルとのレートを一定の範囲内に収めるように市場介入する管理相場制をとっている国もある。
ドルペック制
事実上、世界の基軸通貨はドルである。貿易はドル建てが多くなる。自国とドルとの交換比率が変動すると、自国通貨だてで見た輸出や輸入代金が変動し、貿易に、自国経済に大きな影響を与える。このため、中央銀行が為替介入など行い、自国通貨とドルとの交換比率を一定に保つよう、固定相場制をとっている国が途上国に多い。
ユーロとの連動
欧州においては、ユーロが多くの国で採用されている。このため、欧州の非ユーロ諸国では、欧州内貿易への影響を抑えるため、欧州での基軸通貨といえるユーロに対して自国通貨のレートを一定に保つよう中央銀行が為替介入している国もある。スイスは、中央銀行がスイスフランとユーロとの比率が一定内に収まるように介入していると言われている。
金融政策、変動相場、通貨管理
金融政策、変動相場、通貨管理は、それぞれを独立に決めることができない。ドルとの為替を固定化しようとすれば、政策金利をドルと合わせなければならない。通貨管理されない状態で固定相場で金利差があると、高金利の通貨で運用し、一定期間後に固定相場で低金利通貨に戻せば、確実に利益が得られるため、高金利通貨が買われ、固定相場が維持できなくなる。つまり自由な政策金利は、通貨管理するか、変動相場とするかしか実現できない。国内のインフレをコントロールするには、金利政策が有効で、このため、通貨管理するか、変動相場とするかの選択となる。
為替介入
基軸通貨(通常はドル)に対する自国通貨のレートが為替市場で大きく変動し、自国にとって望ましくない方向に動いている場合、中央銀行が為替市場に介入し、為替レートをコントロールすることがある。これを為替介入という。自国通貨が下がりすぎていると考えれば、中央銀行が為替市場で手持ちのドルを売って自国通貨を買う。上がりすぎていると考えれば自国通貨を売ってドルを買う。中央銀行にとって、自国通貨を用意することは容易であるが、外貨であるドルは手持ち分しか用意できないので、ドル買い介入は容易でもドル売り介入には限界がある。ドル売り介入には、その前に十分な外貨を蓄えていなければならない。為替介入の動機は、明確でない場合が多い。一つは、自国経済に影響が及ぶのを防ぐためといっても、通貨高の影響は輸出業者と輸入業者でまったく異なる。中央銀行が輸出と輸入のどちらを重視しているかで介入行動が異なる。介入の理由づけも不明確になりやすい。急激な為替変動は貿易決済や国際間資金移動に影響し一般的に好ましくない。よって、急激な為替変動を抑えるため、それを理由に市場介入することが多い。しかし実態は、変動の程度より為替の絶対水準に注目し、自国経済に有利となるよう絶対水準を是正するために介入することもある。
国際協調
為替市場は、自国内で閉じた市場ではない。世界中で取引される。ドル円も主に東京市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場で24時間取引される。世界で行われる為替取引量は膨大で、為替介入は、1国だけで行っても効果が薄い。そこで世界の主要国で為替介入により通貨をコントロールする必要性について共通認識ができると、各国の中央銀行が各地の為替市場で同じ目的の為替介入を行うことがある。日本、米国、欧州で協調して行われる場合は、介入効果は大きくなる。また、直接市場介入を行わなくても、核国の中央銀行が協力して金融政策を行えば、為替市場へ間接的に影響力を行使することができる。過去、先進国蔵相・中央銀行総裁会議を通じての協調により為替が大きく動いた。
ドル円レートの性質
日本にとって、輸出の5割、輸入の7割がドル建てとなっていることを考えれば、外貨と円のレートにはさまざまな組み合わせがあっても、ドル円レートが突出して日本経済に与える影響が大きい。ドル円レートの変動メカニズムを分析する。昔、固定相場制だったころは、1ドル=360円であり、為替の変動について考える必要はなかった。変動相場制への移行後、急激に円高となった。短期的な上下動はあっても、長期のトレンドは一貫して円高となっている。その理由としては、昔は米国と比べ相対的に弱い日本が、その後経済発展したことが第一の理由である。日本経済が発展すれば貿易が活発になり、為替市場で通貨の価値が高まる。その間、米国も持続的な経済発展を遂げているが、圧倒的な差があった昔から相対的な差が縮まるについれ、円の価値は高まってきている。経済発展すると、その国の通貨の価値が高まることは、日本以外でも一般的である。管理相場となっている中国を除いて、東南アジアを中心とする新興国の通貨も経済発展につれ通貨高となっている。もう一つの理由は、製造業を中心に輸出が大きく伸びた点である。輸入も伸びているが輸出の方が上回り貿易収支は黒字が続いている。日本企業の海外進出も増加し、海外から受け取る利子や配当も増大している。経済活動で獲得する外貨、特にドルが増えるほど、円に換えた国内に還流させる動きが拡大する。実需筋の円買い需要が持続的に高まっていることが第二の理由である。
短期でも円高となっている理由
経済リスクに対する通貨の反応度の違いが為替相場を変動させる。リーマンショック前は、日本は低金利で米国は高金利であった。このため、低金利の円で調達し、為替市場でドルに換え、高金利で運用する手法(キャリー取引)が盛んに行われた。キャリー取引が増加すると円の売り圧力が高まり、円安が持続する。この状態のまま、経済リスクが高まると、ドル建て金融商品を売却し円に換え、返済してリスク資産を圧縮する反対売買が急増することになる。また、キャリー取引は一般に知られているため、リスクの高まりでキャリー取引の手じまいが増えると予想されると、投機筋の円買いを誘発する。 もう一つは、日米の金利差の変化が為替相場を変動させる。金利差が開けばキャリー取引の魅力度が増し、為替市場で円安となる。金利差が縮小すれば、魅力度が落ち、キャリー取引が抑制されるか反対売買が増えるため円高となる。現在、円とドルは両方政策金利はほとんどゼロであるが、短期から長期になるほど金利は米国の方が高い。よって、中長期金利は常に変動があり、金利差が拡大したり縮小したりしている。米国の中央銀行が政策金利をゼロ近辺にするだけでなく、中長期の金利も低めに誘導しているために、金利差は縮小傾向にある。よって円高が進んだ。
ドル円と経済指標の関係
消費者物価との関係
物価と通貨の価値は相対的関係であるといわれる。インフレは物価が上昇することであるが、モノの価値に対して通貨の価値が下落している状態とも解釈できる。2国間でインフレに差があれば、高インフレ国の通貨の価値が低インフレ国の通貨より価値が下がることになる。円の価値と日米の消費者物価指数との関係を分析してみる。米国では物価が継続的に上昇しているのに対して、日本では93年以降上昇が止まっている。1980年以降は日米で物価上昇率に開きができ、理屈上、物価上昇率の低い日本の円がドルに対して増価することが予想される。実際のレートは予想と整合的である。しかし、物価上昇に差がなかった1970年代でも円高となっていること、90年代後半から00年代前半は物価上昇率の差が拡大しているにもかかわらず、ボックス圏での動きとなっているので、強い説明力があるとまではいえない。
経常収支との関係
経常収支が黒字であれば、貿易や投資の結果で受け取った外貨を自国通貨に変換する力が働き、赤字であれば貿易や投資に対する支払いが多いため自国通貨を売って外貨を得る力が働く。このため、経常収支黒字国の通貨は赤字国の通貨に対して増価することが予想される。1985年以降で、日米の経常収支を比較できる。日本は一貫して経常黒字、米国は程度の差こそあれ一貫して赤字が続いている。円の価値と経常収支との関係は整合的である。リーマンショック時だけは例外で、この時は別の要因が働いたと推測される。米国では1990年以降赤字が拡大しているが、米国は日本より経済規模が大きく、経常赤字の原因が対日収支だけが原因ではないので、赤字の程度と円の増価の程度は直接連動しない。
名目金利との関係
高金利通貨国での運用は、低金利通貨国で資金を運用するより、金利差分だけ得をする。よって、金利差が拡大すると、高金利通貨での運用が更に選好され通貨高となる。米国の金利の変化と為替レートとの関係を見てみる。政策金利と長期金利の代表指標である10年債金利の動きは、1981年まで急上昇し、81年以降はなだらかな低下が続いている。1985年以降は米国金利が低下し円が増価しているので、米国金利と円は逆相関の関係が見てとれる。ただし、85年以前は一定の関係を見てとれないので、説明力は弱い。
実質金利との関係
名目金利はインフレの程度により実質的な金利が変化する。次は実質金利と円との関係性を見てみる。実質金利で見ると、名目金利では説明力がなかった1985年以前についても円と実質金利とで逆相関の関係を見てとることができる。国際分散投資では名目金利が注目される。投資先の国に居住しな限り、投資国のインフレは投資家に影響しないからである。では、実質金利と通貨の価値に関係性があるのはなぜか。実質金利は、名目金利からインフレ率を引いたものである。インフレになるほど実質金利は下がる。名目金利の変化が通貨価値に影響する部分とインフレが通貨価値に影響する部分とが合わさったものが実質金利と通貨価値に影響を与えていると考えることができる。
株価指数との関係
為替市場が動くのは、その売買規模からロンドン市場とニューヨーク市場が開いている夕方から夜間の時間帯である。ドル円が大きく動いた後で日本で株式市場が開く。売買規模は株式より為替市場の方が大きいこと、為替が動いた後に株式市場が開くことから、株価の動きがドル円に影響を与えるというよりもドル円の動きが株価に影響を与えると考えるのが自然である。ドル円と、株価の平均的動きを表す株価指数の動きを比較してみよう。日本経済は、電気、機械、自動車などの輸出型産業が大きな比重を占める。円高となれば輸出企業の業績は低下し、逆に円安となれば業績が向上するため、円高=株安、円安=株高の組み合わせとなることが予想される。30年間のデータで見てみれば、円高=株安、円安=株高となっているのは、驚くことに2000年代後半の5年間だけである。この5年間は、きれいに為替レートと株価指数が相似形となっている。それ以外の1980年代から2000年代前半の25年間は、正の相関はない。むしろ1985年から1988年、1997年から2005年は、逆相関となっていた。円高=株高、円安=株安となっていたのである。しかし、1990年以降の大きなトレンドで見ると、上下動しながらも、円高=株安のトレンドになっている。
ドル円の季節性
為替市場の投資主体である実需筋は輸出入企業である。企業活動は1年間を一つの単位として決まった時期に為替取引をしていることが考えられる。例えばよく言われることだが、日本企業は9月と3月が決算期で9月末、3月末が近づくと、決算処理のため海外で稼いだドルを円に交換するため円高となるとか、クリスマスと年末が来る12月は、世界的にドル需要が増しドル高となるとかである。ドル円の変動率を月別に集計して見てみよう。1年間を見渡すと特徴的なのは、年前半より年後半に円高となる傾向にあることである。特に秋は円高になりやすい。年前半については、記念では奇数月が円高、偶数月が円安となっているが長期で見ると定まった傾向にはない。よく言われる点である3月、9月12月を検証する。3月末が近づくにつれ円高とはなっていないが、9月末が近づくにつれ顕著に円高となっている。12月にドル高となるとはいえない。各月の変化率をつなげて1本のグラフにしてみると、年前半にドル高となり、年後半にドル安となっている。
為替変動の謎を解く
為替相場のテーマ性
買い手と売り手で構成されるマーケットには、株式市場、債券市場、商品市場などがある。株式、債券、商品などは通貨によって価値を表され、株式、債券、商品と通貨との間で取引される。リスクが意識されれば、株式、債券、商品が売られ現金が選好される。それらと為替市場が大きく異なる点は、為替は通貨間の相対価値を表し、リスクが意識された時の逃避先の現金がない点である。あくまで相対的関係で、株式、債券、商品のように現金で絶対価値が測られるものでない。ある通貨が売られれば別の通貨が買われる。株式、債券、商品はリスクに応じて上下に変動するのに対して、為替の動きは複雑となる。為替がどのようなテーマに注目が集まり、為替の動きが現れるか時系列で追ってみよう。
米国経済が好調な時代、ユーロや円よりもドルが買われ、ドル高が進んだ。世界景気が全体的に好景気となると、高金利通貨であるユーロやポンド、豪州ドルなどが買われた。円は低金利通貨の代表格で、低金利の円を売って高金利通貨を買う、キャリー取引が盛んになった。ドルの金利が上昇すると、ドル円間でもキャリー取引が活発になり、円安ドル高が進んだ。より高金利通貨であるユーロや豪ドルに対しては、ドル安高金利通貨高が続いた。日本では、FX取引が拡大し、個人投資家の円売り外貨買いにより円安が更に進んだ。しかし、米国のサブプライム問題で米国通貨のドルの信頼が揺らぐと、キャリー取引の巻き戻しで円高に、ドルからの逃避でユーロ高に進んだ。世界景気後退懸念から、先進国各国の金融緩和が進んだが、ドルの利下げが先行したこと、欧州は比較的底堅かったこと、日本ではすでに低金利で利下げ余地がなく、日米金利差が縮小していったことにより、急激な円高、ユーロ高となった。ドル安の進行でドル建ての商品価格、特に原油価格は急騰したが、米国に続き、欧州での景気後退が確認されると、急騰の反動からユーロが急落した。ドルやユーロから逃避したマネーの行先はもともと低金利通貨でキャリー通貨でもあった円やスイスフランに集中した。ユーロとの連動性が強いスイスフランより円にマネーが集中し、他の先進国通貨が下落するのに対して円だけが急上昇した。その後、日本経済も深刻な影響を受けたことが判明し、円が売られたが一時的なものとなり、再び上昇した。リーマンショックが起きると、有事に強いドルとして、世界経済における唯一の現金であるドルへの逃避が起き、ドルが買われ、他の先進国通貨は下落した。ただし円は例外で、円高が続いた。リーマンショック後、世界景気は回復し始めたことで、売られていたユーロが買われるようになった。米国の長期金利の上昇で、円は再び売られるようになった。米国で景気の回復が弱まると、米国で量的緩和が実施され、ドル全面安の展開となった。 為替市場では、米国の金融政策に関心が集中しやすく、繰り返された政策金利の利下げ、長期金利の低め誘導、大規模な量的緩和でドルの価値が下がり、相対的に他の通貨が高くなった。米国の長期金利は更に下がり、円高が進んだ。
実需と投機
円高が大きなニュースになっています。現在1ドル76円台となっており、史上最高値水準にあります。円高は輸出企業の採算を悪化させ、輸出で稼ぐ日本経済にとっては悪い影響があると言われています。この望ましくない円高の「犯人探し」の結果、投機的取引を行うヘッジファンドがやり玉に挙がっています。投機的取引の状況が読み取れるシカゴ取引所のデータによると、投機筋が円を買い越すと為替が円高となっていることが分かります。これが投機筋が円高の犯人とされる理由ですが、投機筋だけが円高の原因でしょうか。シカゴ取引所のデータをよく見ると、確かに投機筋が円を買い越すと円高となっていますが、逆に投機筋が売り越したときは円安とはなっていません。投機筋が円を売るときに、それを買う参加者がいることを示しています。その参加者は、投機筋が円を買う時も売る側には回らず、その結果円が大きく上昇し、投機筋が円を売る時はそれを吸収していると仮定すれば、データとの整合性が見てとれます。この参加者は常に円を買い続けていると推測できます。この実体は何でしょうか。近年の円の為替レートは、07年を除いて10年間の長期に渡って、ほぼ一本調子で上昇しています。外国人が中心となる投機筋は、外貨である円の差金決済で利益を上げることを目的としていますので、円を買ったらいつかは円を売って決済させます。円を買い続けることはありません。つまり、ある期間で見れば、売りと買いは同量なのです。短期的には円相場の上げ下げに影響を与えますが、長期的には相場への影響は中立です。一方、貿易等の事業活動で円を売買する実需筋は、反対売買は前提にされません。例えば、輸出企業なら海外で稼いだドルを円に変えたらそのままで、反対売買(円売りドル買い)はありません。円を買ったら買いっぱなし、売ったら売りっぱなしです。日本の近年の国際収支統計を見ると、所得収支の黒字が大幅に伸びているのが分かります。所得収支の黒字は、海外投資で得た利子・配当が国内に送金されていることを表します。この過程でドルが円に変えられます。つまり、海外投資で稼いだ国内企業が、年々、円買いの量を増やしているのです。このため、長期に渡って円高が続いているのです。投機筋は、短期的な為替相場の上下動を形作っているだけです。円高の真の主役は投機筋ではなく、日本企業だと言えます。
金融政策
米国側の要因としては、米国内景気を回復させるために取られている金融緩和の影響です。政策金利や短期金利はゼロ近辺に維持されています。長期金利も歴史的低水準です。低金利を維持するために、中央銀行が大量のドルを市場に供給しています。ドルが大量に世の中に出回れば、ドルの価値、すなわち他通貨に対する相対的価値は低下します。他通貨に対して低下するということは、円に対しても低下します。金利の低い通貨で資金を調達し金利の高い通貨で運用する、いわゆるキャリー取引は、為替の変動が小さければ安定的に利益を出す方法です。金利の低下(米国債価格の上昇)は、日本から新規の米国債投資を抑制し、米国債の売却と資金の国内還流を増大させます。その結果、円が買われ円高となります。以前、日米金利差が大きかった頃は、低金利の円を売ってドルに変え高金利で運用する手法が普及し、その結果円安となっていましたが、近年の米国の金利低下による日米金利差縮小で、円高が続くようになりました。先進国では低インフレ時代となっています。インフレにならないので金利が低い状態が続くようになりました。米国の金利は、ここ20年に渡って金利低下のトレンドが続いており、日米金利差が今後再び大きく拡大する可能性は小さいといえます。つまり円安にはなりにくい、円高が定着することが予想されます。
理論価格
為替レートには「理論価格」というものがあり、市場で日々動く為替レートは、やがて理論価格に収れんしていくとの考え方があります。理論価格の一つに、購買力平価仮説があります。モノの価値は世界どの地域でも同じで、すなわち価格が世界共通であるとする説です。ある商品の価格が日本で100円であり、まったく同一の商品が米国で1ドルで売られていたとすると、商品の価値は日米で同じと考え、その結果100円=1ドルが妥当な為替レートとなるわけです。理論としては単純ですが留意点があります。同一の商品といっても、生産地が一つで販売先が世界各地である場合は、輸送費や関税などが異なり、同じ商品なら同じ価値(価格)とは厳密には言えません。もうひとつは、そもそも同じ商品は世界どこでも同じ価値かという疑問です。市場価格は需要と供給で決まります。需要も供給も時間とともに時々刻々と変化し、その結果価格も変化します。それならば、場所によって商品の需給関係が変化していても不自然ではありません。地域によって消費者の収入水準、原材料価格、輸送費などが異なるため、価値(価格)が異なることもありえます。この場合、価値が同じとの前提で、円建て価格とドル建て価格をイコールとして考えることはできません。しかし、絶対的な為替レートを計算できないとしても、為替レートの変化を理論的に計算することはできます。ある商品の円建て価格が5%上昇し、ドル建て価格が不変であるとしたら、円がドルに対して5%下落したと解釈するのです。個々の商品の価格の動きでは、商品固有の需給関係の事情で動くこともありますから、様々な商品の全体的動きを表す消費者物価指数の動きから為替の理論的な動きを計算します。例えば日本の消費者物価指数が1年で1%上昇したとき、米国では同じ期間に3%上昇した場合、ドルの価値が円に対して2%(3%-1%)下落したと考えます。理論的には1年で2%円高となるわけです。過去20年の日米の消費者物価指数の変化を見ると、米国の消費者物価指数は、一貫して毎年2~4%上昇しているのに対して、日本の消費者物価指数は、-1~1%であり、相対的に円の価値が一貫して上昇していることになります。円の理論値がドルに対してずっと上昇しているため、実際の為替レートでも、長期のトレンドとしては円高になると説明されます。
インフレ
消費者物価指数の日米差が為替レートの変化をもたらすという理論は、長期の統計においては、ある程度の説明力がありそうです。しかし、短期的な動きを説明するものではありません。長期の為替レートの動きを説明する理論であるならば、ドル円だけでなく、他の通貨の為替レートにおいても説明力が求められます。ユーロドルの場合、欧州と米国では、消費者物価指数の差は日米ほどはありません。しかしユーロドルの為替レートは大きく変動しています。ユーロ円の場合、欧州では消費者物価指数は上昇、日本では横ばい又は下落です。この理論によると、ユーロ円はずっと下落することになります。最近のユーロ危機でユーロ円は下がっていますが、リーマンショック前まではユーロ円は上昇していました。新興国通貨とドル、又は新興国通貨と円の場合はどうでしょう。一般に、新興国の方が日米などの先進国よりインフレ率が高く、理論によれば新興国通貨が先進国通貨より下落することになります。実際の為替レートでは、リーマンショック時とユーロ危機時に新興国通貨は下落していますが、それ以外の期間では、新興国通貨がずっと上昇しています。一般に、経済が大きく成長している国は、インフレ率も高い傾向にあります。中央銀行はインフレを抑えるために金利を高く維持しています。高金利通貨は投資家にとって魅力であり、為替市場で買われやすくなります。経済がさらに発展しさらにインフレの可能性が高まると、経済の発展によるその国の通貨の需要増と、さらなる高金利の期待から、為替市場で買われ通貨高となります。金利が高くてもその分インフレであれば実質金利は低くなります。自国民にとっては実質金利が重要ですが、外国人にとっては、その国で生活することはないので名目金利だけが重要となります。高インフレ率の通貨は名目金利が高く、外国人に買われやすくなります。このため、相対的にインフレ率の低い通貨の為替レートが上昇するという理論は、当てはまらない場合が多いと言えます。
相対的関係
為替は2つの通貨の相対的価値を表します。ドル円のレートが円高となった場合、円の価値がドルに対して上がったことであり、ドルの価値が円に対して下がったことでもあります。円とドル、どちらの通貨が原因となっても為替は動きます。他の為替レートの動きも合わせて見れば、どの通貨の動きが大きかったか分かります。円ドル、ユーロドル、ポンドドル、スイスフランドルのチャートを見ると、過去一定の傾向があるのが分かります。ユーロドル、ポンドドル、スイスフランドルは同様な動きをします。これは、ドル以外の通貨が同期して動くというよりは、むしろドルが他の通貨に対して変化していることを意味します。一方、円ドルはそれらとは異なる動きをします。円はユーロ等の他の通貨ともドルとも異なる動きをするようです。通貨そのものの価値を測る指標に、実効為替レートがあります。実効為替レートで見ると、ドルは長期的には下落トレンド、円は上昇トレンドとなっています。ドル円の動きと説明できます。実効為替レートに物価の影響を除いたものが実質実効為替レートです。日本はゼロインフレ、米国等の外国はインフレであるので、実質実効為替レートで見た円は、ドル円のトレンドほどは円高とはなっていません。国内物価が安く保たれているために、国内生産品を輸出する場合、物価上昇の続く諸外国に対して、円高による価格競争力の不利を和らげるよう働きます。